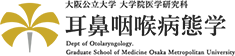めまい外来は毎週月曜日に行っております。現在めまいを主訴に受診された患者様は初診時に眼振検査、聴力検査、血液検査などを行い、後日に温度刺激検査や視運動眼振検査・追跡眼球運動検査、必要があれば頭部の画像検査、vHIT、VEMP, Foulage test(足踏み検査)、Head Up Tilt (Schellong試験)、蝸電図検査などを行っています。また、難治症例に対しては入院下でのリハビリテーションなども行っております。
– 良性発作性頭位めまい症
浮遊耳石置換法を行っています。
– メニエール病
めまいの発作頻度が多く、内服、点滴等でコントロールが困難な患者様には中耳加圧療法を施行しております。
– 起立性調節障害(自律神経機能異常を含む)
ふらつきの原因として疑われる場合にはHead Up Tilt試験を行い、確定診断後に薬物治療を中心とした治療を行います。
– PPPD
慢性的なめまいの代表的疾患で治療法は確立されていませんが、入院下のリハビリテーション(リハ科と協力)などを試みています。
当院では
詳細については下記リンクをご参照ください。 大阪公立大学医学部附属病院にめまいで受診された患者様へ